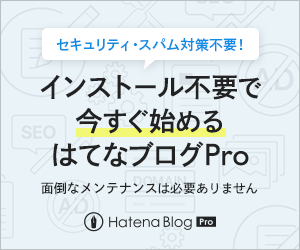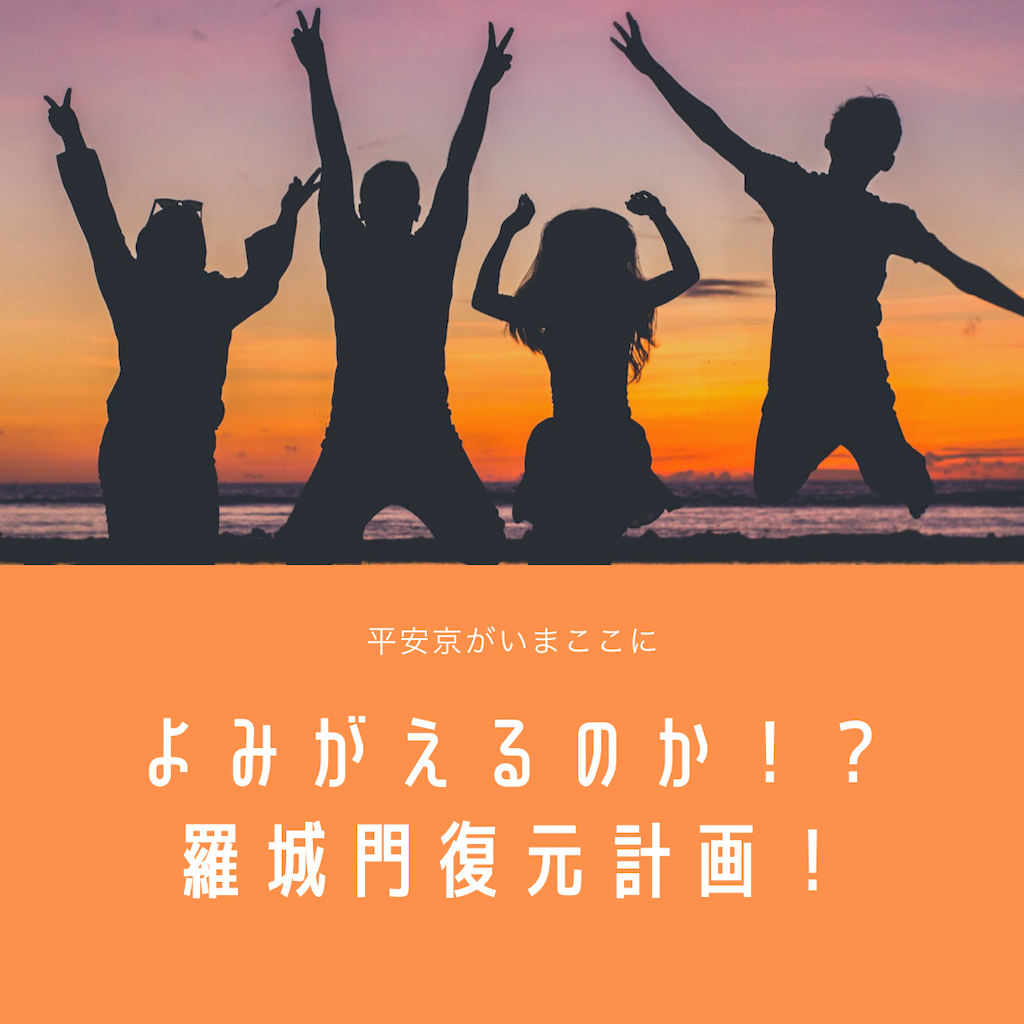
平安京の正面玄関でもある「羅城門」。
今ここで「羅城門の復元計画」が持ち上がっています。
前回も「安土城復元計画」について書かせていただきましたが、やはり歴史的建造物の象徴として、そして理解を深めるためにも、壮大な復元に注目が集まっているようです。
その時の「安土城復元計画」についてはこちらから。
こちらは門どころか城まるごと復元計画ですので、なかなかの規模の大きさとなっています。
どんな風に復元されるの?
復元ってどのくらいの大きさでするのかしら?模型なら見たことあるけれど…
復元っというからには原寸大!かなり大きな物になりそうね。
時間もお金もかかりそう…
復元というからには、当時の大きさのまま、原寸大の伝統的な木造工法で再建されるようです。
もちろん現代風に、耐震、耐火、耐風などの対策はとられます。
それではこの羅生門とはどんな建物だったのでしょうか。
羅城門って何?
そもそも羅生門とは、人々が疫病や戦火などから身を守るために建てられました。
816年に大風により倒壊し、その後再建されるも980年に再度大風で倒壊。
2度の倒壊の後、再建されることはありませんでした。
平安京のメインストリートである朱雀大路に建てられた羅城門は、794年前後に建築され、約100年もの間、その役割をになっていました。
門の大きさは
・幅 80メートル
・高さ 24メートル
・奥行 21メートル
で、門は入母屋造。瓦屋根にはしびがのっていました。
また木部は朱塗り、壁は白土塗りの作りで、都の正門にふさわしい、色どりでもあったのですね。
JR京都駅前の羅城門こんな感じ


これは2018年12月、たまたま通りすがりに撮ったものです。
このスケールで原寸大の10分の1の大きさの模型となります。
夜になるとライトアップもされ、後ろの京都タワーとのコラボレーションがとても魅力的でした。
まとめ。歴史とは何か
こういった当時の再現、復元というのは、その時代への理解や歴史的背景を深めるのにも非常に役に立ちます。
私たちが歴史を勉強する上で大切なことは、ただただ事実を覚えるというわけではなく、しっかりと
事実を確かめ、推論し、考えその意味を探ることであると思っています。
イギリスの歴史家であるEHカーは
『歴史とは現在と過去との絶え間ない対話である』
という言葉でその歴史学について語っています。
現在当たり前にある解釈が、本当とは限らないですからね。
だから歴史は奥深く、研究し甲斐がある学問なんだと思います。
少し話題はそれましたが、この再建計画については、2020年10月現在では、場所や費用、完成見込みなどはまだ決まっていません。
時間はかかりそうですが、この「よみがえる羅生門プロジェクト」
果たしてよみがえることができるのか。注目していきたいと思います。
ランキングに参加しています。応援お願いします!